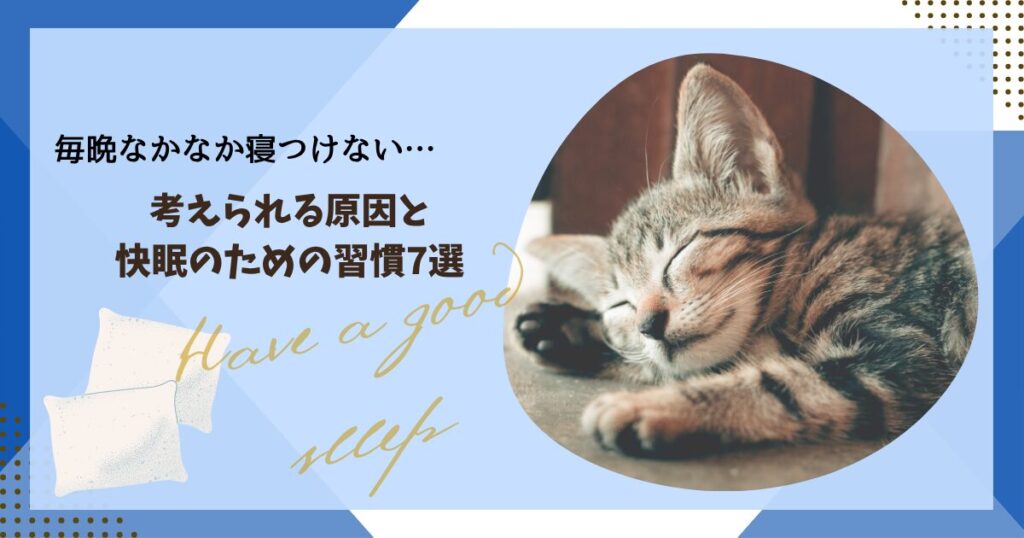「布団に入ったのに、なかなか眠れない」「明日早いのに、どうしよう」
そんな夜、ありませんか?
眠れない時間が続くと、心も体もじわじわと疲れていきます。
「なんで寝つけないんだろう?」と考えれば考えるほど目が冴えてしまう…そんな経験をした人も多いのではないでしょうか。
寝つきが悪い原因は1つではなく、日々の生活習慣やストレス、寝室の環境など、さまざまな要因が絡み合っています。
この記事では、寝つきが悪くなる代表的な原因と、今日からでも始められる快眠習慣を7つご紹介します。
「できることから、少しずつ」。
あなたの眠りが、少しでも心地よくなるきっかけになりますように。
毎晩なかなか寝つけない…その悩み、あなただけじゃない
毎晩のように「なかなか眠れない…」と感じている方は、実はとても多くいます。
厚生労働省の調査によると、成人の約20〜30%が「不眠の症状を感じたことがある」と答えています。
つまり、寝つきが悪いことは特別なことではなく、誰にでも起こりうる身近な悩みなのです。
仕事や育児、人間関係のストレスに加えて、スマホやカフェインなど現代特有の要因も重なり、眠れない夜が生まれてしまいます。
まずは「自分だけじゃない」と少し安心して、原因を一緒に見つめ直してみましょう。
寝つきが悪い人の共通点とは?
寝つきが悪い人に共通するのは、眠る直前まで「脳や身体が休めていない」ことです。
たとえば、
布団に入る直前までスマホを見ていた
明日のことをあれこれ考えてしまう
カフェインを夕方以降にも摂っている
こうした行動は、脳を興奮状態にしたまま眠ろうとしているようなもの。
さらに、就寝・起床の時間がバラバラだったり、寝室の環境(音や光)に敏感な人も、スムーズな入眠が難しくなる傾向があります。
「眠る準備」ができていない状態のまま布団に入っても、自然に眠れるとは限らないのです。
よくある誤解「疲れてるのに眠れないのはなぜ?」
「今日は疲れたからすぐ寝られるはず」と思っていたのに、目が冴えてしまって眠れない…。
そんな経験、ありませんか?
これは「身体の疲労」と「脳の緊張」がズレている状態で起こります。
身体はクタクタなのに、頭の中では
「明日の予定どうしよう」
「さっきの会話ちょっと気になる」
…など、思考がぐるぐる回っている状態です。
疲れ=寝落ち、とは限りません。
むしろ疲れすぎて交感神経(活動モード)が優位になり、逆に眠れなくなることもあるのです。
「疲れているのに眠れない」は、緊張をほどく準備が足りていないサインと捉えると、改善のヒントが見えてきます。
寝つけない原因は1つじゃない|代表的な7つの理由
寝つきが悪くなる理由は人それぞれですが、多くの人に共通する「代表的な原因」がいくつかあります。
意外と無意識にやっている習慣が、睡眠の質を下げていることも…。
ここでは、寝つきが悪くなる原因としてよく挙げられる7つのポイントを紹介します。
思い当たるものがないか、チェックしてみてください。
日中のストレス・不安
ストレスや不安は、睡眠に最も影響を与える要因の一つです。
心配ごとやモヤモヤした気持ちを抱えたままでは、脳がリラックスできず交感神経が優位な状態が続いてしまいます。
このままだと、眠ろうとしても頭がフル回転したままで、寝つくのが難しくなってしまうのです。
ストレスとうまく付き合う工夫が、質のよい眠りへの第一歩になります。
スマホ・PCのブルーライト
寝る前にスマホやパソコンを見ていませんか?
それらの画面から発せられる「ブルーライト」は、脳を昼間と錯覚させ、睡眠ホルモン(メラトニン)の分泌を抑えてしまいます。
SNSや動画を見てリラックスしているつもりでも、画面を見続けることで知らず知らずのうちに覚醒状態になっている可能性も。
寝る1時間前は、できるだけデジタルデトックスの時間にするのがおすすめです。
カフェインやアルコールの摂取タイミング
カフェインはコーヒーだけでなく、緑茶や紅茶、チョコレートにも含まれています。
摂取してから5〜7時間ほど体内に残るため、夕方以降の摂取は寝つきを悪くする原因に。
また、アルコールは一見眠りを誘うように思われがちですが、実は睡眠の質を下げる作用があります。
夜中に目が覚めたり、浅い眠りになってしまうので注意が必要です。
生活リズムの乱れ(就寝時間のばらつき)
平日は寝るのが遅く、休日は昼まで寝ている…という生活をしていると、体内時計が乱れて眠りのリズムが崩れてしまいます。
体は習慣に敏感なため、「今日はもう寝る時間だよ」と伝える一定のリズムが大切です。
就寝時間と起床時間をなるべく固定することで、自然と眠気が訪れるようになります。
寝室の環境(明るさ・音・室温)
音が気になる、明るすぎる、暑すぎる・寒すぎる…。
こうした**「ちょっとした不快感」が、寝つきを邪魔する大きな要因**になります。
また、自分では意識していなくても、寝具やパジャマが合っていないことも睡眠の妨げになることがあります。
自分にとって心地よい「眠れる環境」を整えることはとても大切です。
枕やマットレスが合っていない
「寝つきが悪い」と感じている人の中には、枕やマットレスが合っていないだけというケースもあります。
高さや硬さ、素材などが合っていないと、無意識のうちに何度も寝返りを打ち、寝つきにも影響が出てしまいます。
自分の体格や寝姿勢に合った寝具を選ぶことが、快適な眠りへの近道です。
寝る直前まで頭がフル回転している
寝る前に「明日の予定を考える」「今日のミスを思い出す」など、頭を使うことをしていると、脳が休まらず眠れなくなってしまいます。
布団の中でスマホを見るのも、頭が情報でいっぱいになってしまう原因のひとつです。
眠る1時間前は「何もしない時間」をつくり、深呼吸やストレッチ、アロマなどで頭と心をほぐすのがおすすめです。
今夜から取り入れたい快眠のための習慣7選
寝つきが悪い原因がわかったら、次は「どうやって改善していくか」が大切です。
とはいえ、全部をいきなり変える必要はありません。
ここでは、今日からでも無理なく始められる快眠習慣を7つご紹介します。
あなたの生活に合いそうなものから、少しずつ取り入れてみましょう。
寝る1時間前はスマホを手放す
ブルーライトを避けるためにも、寝る前のスマホやテレビは控えるのが理想です。
代わりに、本を読んだり、音楽を聴いたり、「脳を落ち着ける」時間に切り替えてみましょう。
難しい場合は、夜だけ「ナイトモード(ブルーライトカット)」を設定するのも効果的です。
リラックス効果のあるお風呂に入る
38〜40℃程度のぬるめのお湯に10〜15分浸かると、副交感神経が優位になり、心と体が自然とリラックスモードに。
入浴後に少し体温が下がるタイミングが、ちょうど眠りやすいタイミングでもあります。
好きな入浴剤やアロマオイルを使うのも、習慣化しやすくなるポイントです。
ノンカフェインの飲み物を選ぶ
夜に何か飲みたいときは、ノンカフェインのお茶やハーブティーを。
カモミール、ルイボス、ラベンダーなどにはリラックス効果もあると言われています。
身体を内側から温めることで副交感神経が働きやすくなり、自然な眠気が訪れやすくなります。
室温と照明を「眠れる環境」に整える
理想的な寝室の温度は、夏は26〜28℃、冬は16〜19℃前後とされています。
エアコンを使うときは、冷えすぎ・乾燥しすぎに注意を。
また、照明は間接照明や暖色系の光に切り替えると、より眠りに入りやすくなります。
夜の時間は「少し暗め」を意識すると、体内時計も整っていきます。
枕・寝具を見直す
枕やマットレスが合っていないと、どれだけ工夫しても眠りの質は上がりにくいもの。
最近では、「横向き寝に特化した枕」や「高さ調整できる枕」なども増えているので、自分に合うものを見つけてみましょう。
朝の光を浴びてリズムを整える
朝起きたら、カーテンを開けて自然光を浴びることを習慣にすると、体内時計が整いやすくなります。
太陽の光には、メラトニン(眠気を促すホルモン)のリズムをリセットしてくれる効果が。
朝の行動を見直すことで、夜の寝つきにも良い影響があるのです。
寝る前に簡単な呼吸やストレッチをする
布団の中でできる軽いストレッチや、深くゆっくりとした呼吸を繰り返すだけでも、体は自然とリラックスモードに。
おすすめは「4秒吸って、7秒止めて、8秒吐く」呼吸法や、手足をゆっくり伸ばすストレッチ。
心が静かになるだけでなく、眠気も引き寄せやすくなります。
まとめ
寝つきが悪くなる原因は、決してひとつではありません。
ストレスや生活習慣、寝具の不一致など、いくつかの要因が重なっていることが多いのが現実です。
でも、心配しすぎなくても大丈夫。
小さな習慣を見直すだけでも、眠りの質は着実に変わっていきます。
「全部やらなきゃ」と思うと負担になりますが、
まずは今日から「寝る前にスマホをやめてみる」「ノンカフェインのお茶を飲んでみる」など、できそうなことから始めてみてください。
眠れる夜が少しずつ増えていくと、心と体が元気を取り戻していくのを感じられるはずです。
あなたに合った快眠習慣が見つかりますように🌙